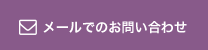学校長ブログ
アウトプットの力
「なぜ?」を問うこと
授業を大切にする
時代の「空気」、そして「未来」
書の「道(みち)」
運命の女神に好かれる
ホモ・ファーベル
山より大きなイノシシはいない
授業はエンターテイメント!
「心」が変われば、学校が変わる
生徒の側に立つ
改善あるのみ!
なごやかに、ゆるやかに
中央らしい授業を
授業ができる喜び
さて、今年の学習合宿は?
おすすめです!中央特進
生徒の心に火をつける
保健室に行きました!
『ボッチャ』って何だ?
救命救急講座に参加しました!
ゴンドーシャロレーにて
自分を見つめ直します。
夏頑張る、春微笑む
優秀な教師が評価される時代
今日、ヒロシマ原爆忌
歌に思いをのせて
あなたはわたしの夢だから
やります!面白い数学の授業を
君に捧げる応援歌
本日、早朝7:00。中央書道部が松山で行われる『書道パフォーマンス甲子園』に出発しました。初出場です!中央に書道部ができた頃を思い出します。
歩んできた道に仲間がいて 忘れることはない
嬉しかった日 悔しかった日 共に泣いた日 共に笑った日
-Hippy『君に捧げる応援歌』-
書道の経験者がいたわけではありません。施設や道具がそろっていたわけでもありません。紙もない、場所もない・・・そんな中で力を合わせ、けっしてチャレンジをあきらめなかった。実績のある生徒達を集めて成果を出す。多くの私学がやっていることとはまったく逆です。一から自分達で考え、努力し、時には涙を流し、悔しさを乗り越え、ひたすら前へ前へと歩んできた。書道パフォーマンスもまたしかり。どれだけ失敗したでしょう。笑われたり、蔑まれたり、挑戦してもなかなか予選を通過できなかった・・・でも、そういった歴史が、ほろ苦くも忘れられない足跡を残しました。
みなさんはどう思われるでしょう。教育って、本来、こうでなければならないとわたしは思います。繰り返しますが、実績のある生徒を集めて成果を出す。誰のため?学校のため・・・でも、それは違うでしょうって言いたい。
優勝するとかしないとか、そんなことよりも真の教育がここにあるということ、あきらめない、めげない、くじけない生徒達がここにいるということを声を大にして訴えたい。
初の全国大会。
立ち上がろうとする君に捧ぐ 君への応援歌 全力注ぐ
負けそうなときは思い出してよ 過ごした日々をこれまでの足跡
-Hippy『君に捧げる応援歌』-
全国に届け~中央書道部の書の力!そして飽くなきひたむきな思いよ。新たな一歩が、また次の一歩へ。がんばれ、書道部!
元気と勇気を届けたい!
三本の矢
スイカと夏のサプライズ
国試の合格率より大切なこと
みなさんに支えられています。
表現できない何か
ものさしは一つではない
伝統の力
子どもは小さな大人ではない
3つの力で
時代は、課題発見力です。
ほんとうに変わるべきもの
何のためのテストだろう?
返事のある教室
コロナ感染の中で
約束したので
授業=我慢ではない!
続・授業を極めたい
授業を極めたい
先日、数学科の百田先生に
「塩田先生が、昨年言っていたこと、今なら少しわかるような気がします。」
と言われました。正直、何のことか覚えていませんが・・・笑 普段、無駄な雑談はしないので、もちろん授業のことでしょう。自分は成長したってことかもしれません・・・笑
さて、今日は家庭科の田島教生の研究授業です!
「まず初めに、総合探究コースのみなさんに関係のある話から始めます。水検定です。」
明るい笑顔とはきはきとした言い回し。こんなことを言っては何ですが、やはり見た目も大切です。そこは勝てない・・・笑 時間にして2時間。ひとつひとつしっかり丁寧に授業が進んでいきます。2年5組の生徒達も先生の問いかけに何とか言葉を返そうとがんばりました。授業は教師と生徒で創るもの・・・教師だけがどれだけ力んでも、けっしていい授業にはなりません。
「おっ、すごい・・・」
生徒からの声に、控えめに驚く田島教生のリアクションが印象的でした。
学校をよくしたい!
権威を疑う
中央総ビのサクセスストーリー
一人の出来事をクラスの教材に
担任をしていた頃、連絡ばかりの朝は嫌いだったので、連絡はペーパーにして副委員長に後ろの黒板に書かせていました。確認するのは自分たちの責任。何でもかんでも話で伝えると賢くなりません。むしろ甘えます笑。で、わたしは話をする、いや、話をする時間を作る。何を話すのか?見たままを話すのはNGです。寝ている生徒に寝るな~別にいいのですが、それでは生徒達は考えたり、気づいたりしません。だから「教材化」して話す。ここが技です。ようするに「なぜ?」のポイントを絞る・・・一人の出来事を「教材化」してクラス全員で考える材料にする。問題はいくらあってもOKです!そのすべてが「教材」になるから・・・
感じる心
好きに優るものはない
教え方のプロ
若者に学ぶ時代
「なぜ?」と「アウトプット」
生徒を見るということ
母校に錦を
「どうせ」と「まあいいや」
スーパーダンディー徳本
教師になりたい!
生きていく強さを
すべての高校生にエールを
中央生は本番に強い!?
教えることは学ぶこと
能ある鷹は爪を隠す
担任の腕
今日から2年生
ザ・一宮ワールド
新たな一歩を
次は動画鑑賞、TEDトーク『キャロル・ドゥェック教授 必ずできる!未来を信じる「脳の力」』が始まります。
生徒にとって意味がある、ためになると確信を持てたものをどんどん授業で使っていく。日頃からその意識がないとなかなかできません。小森先生、よく勉強しています。すばらしい。
「校長先生が授業を見に来るの、3段階ぐらいにしてもらえませんか?明日はまず第1弾・・・」
なんて謙遜していましたが、どうしてどうして感心ばかりですよ、先生笑。
小森先生の新たな一歩が、次の一歩、また次の一歩へと・・・熊本中央高校で紡がれていく。楽しみです。先生の物語に幸多からんことを~
中央アートの先導者
教師の実力
ほんとうに大切な4つの力
グランドピアノ、お披露目です!
掃除道
思いを力に
テストが物語るもの
学校は、必要なんです。
無垢でピュアでハートフル
すべてのことに意味がある
孤軍奮闘
言葉の力
今日は書道部!
「聞く」ということ
教室に入ると、「おはようございます!」というたくさんの声。
「先生、何しに来たんですか?」
「見学に来た。」
雨曇りの天気とは対象的に、明るい笑顔がウェルカムしてくれます。
週明けの教室訪問は、1年9組教室。
看護科のお母さん、大ベテランの先生が担任のクラス。明るく屈託のない雰囲気から、よくかわいがられているのが伝わってきます。ベテランの味というやつです笑。
「今日は連絡事項がたくさんあるから、LHRの時間も併せて伝えますね。」
そんな担任の言葉に、教室は一瞬で静かになり、連絡ノートを出す生徒達。
今年の1年生はすばらしいです。入学以来、「うるさい」とか「静かにしろ」なんて不適切な言葉を校内で聞いたことがありません。
きっとわかっているんだと思います。そもそも学校は話を「聞く」場所であることを。
きっとわかっているんだと思います。話を「聞く」ことができないと損をするということを。
看護師という夢。-
それを必ず叶える!まだ幼い瞳の奥に、しっかりとした決意が芽生えるだろうことを期待しながら教室を後にしました。
いざ、体育祭へ
「一発勝負だよ!わかってる?」
「わたしは、むちゃくちゃ頭にきてるんだけど!」
「ソーラン節はとりだよ、最後だよ!誰かの気持ちがゆるんだら、今年の3年はこんなもんかって思われる!」
「わたしは、できるまで何回もやるからね!」
熊本中央高校が誇る熱血ウーマンが吠える、吠える。熱い、熱い。
歳のせいか、うるうるとじーん、じーんが繰り返される笑。わたしは、この熱血ウーマンの熱さが大好きだ笑。
明日は体育祭。数年ぶりのフルーバジョン。中央恒例、プログラム最後の3年ソーラン節、最後の指導に熱が入る。
なんとしても素晴らしいものにしたいという思い。-
感動は目には見えない。がんばればがんばるほど青春は輝く。仲間とともにその一瞬に挑む。
わたしもわくわくがマックスだ。
「中央らしい」体育祭。きっと生徒達が見せてくれるだろう。
根っこって何だ?
若手のハイパーフォーマンスMCティーチャーの朝のHR。1年3組。
← いきなり読み始めた詩。しんみりと聞き入る生徒達。
「この詩で、根っこって何だと思う?」
「えっ、うーん、がんばる動機みたいな・・・笑」とある生徒
ティーチャーはおもむろに語りだす。高校時代にお母さんの弁当のかわりに内緒で購買のパンを食べていたこと。それを、先日お母さんにあやまったこと。その時、お父さんが、「お前、母さんが何時に起きていたのか知っていたのか?母さんは4時半に起きていたんだぞ」と言われて、自分が支えられていたこと、自分という花を、たくさんの枝や幹や根っこが支えてくれていたこと。を-
「みんなは今、花かもしれない。でも、花には必ず根っこがある。いいクラスとは、誰もが花になれて、誰もが根っこになれるクラスだと思う。」
こんなにいい教師だったかな・・・笑。わたしもうっかりしていた。
ただし、「校長先生がいるからこんな話をしたわけじゃないんだよ笑。」という台詞は余計です笑。いいHRでした~
老骨に鞭打って
ただ、ひたすら教壇に立ち続ける教師がいます。
ただ、ひたすら教えることにこだわる教師がいます。
ただ、ひたすら生徒達とかかわる教師がいます。
中央高校最年長、とってもチャーミングな英語の先生の授業にお邪魔しました。
「先生、今日の授業の前半を見学させてもらっていいですか?」
「えっ、特別なことは何もしませんよ笑」
「あと・・・怒らないでくださいね・・・」
「何ですか?」
「ブログ書くんですけど・・・“老骨に鞭打って”という言葉を使ってもいいですか?」
「もちろんです。老骨に鞭打ちまくっていますから笑」
授業の開始からオールイングリッシュ。元気いっぱいです。
「Who is your favorite writer?」
「What sports do you like?」
「Do you belong to the badminton club?」
とてもわたしには聞き取れない英語、英語、英語・・・。先生は、かまわずぐいぐいとオールイングリッシュ。元気に答える生徒達。
ただ、ひたすら授業をする。いくつになろうと、ただ、ひたすらに。老いてもなお授業をする。われわれ教師にとっての授業、その根っこにある大切なことを、あらためて今日の授業で教えられた気がしました。
二刀流!?
「明日、朝のホームルーム見に行くから~」とわたし
「えっ、見に来るんですか?」
「そうだよ。だめ?」とわたし
「いやー、わかりました笑」
今朝の教室訪問は、こんな適当な感じで決定しました笑
1年2組、普通科芸術創造コース。
いつもスーツで、礼儀正しく、生徒思い。
いつもにこやかで、きちんとしていて、生徒にやさしい。
担任は、個性的な教師が多い中央で、屈指の常識派、この人に任せておけば間違いないという先生です。連絡事項も、口頭だけではなく、黒板にきちんと書く。
1限目進路講話があるということであわただしく終わった朝のホームルーム。そこで注目すべき画像を発見!
「写真撮っていい?」とわたし
「はい」
「美術なの?」とわたし
「いいえ、音楽です!」
きらきらした笑顔、音楽でもこれだけの絵のセンス。まさに二刀流。熊本中央高校芸術創造コースは、才能の宝庫だなあ、とあらためて感心しました。